
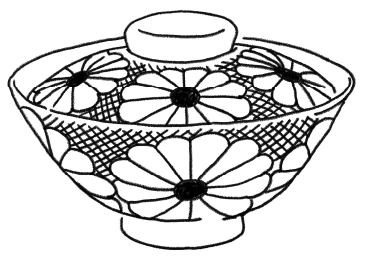

生活のなかで、もっとも頻繁に使う日用品といえば、食器や器ではないだろうか。自炊をまったくしない、食器を洗うのが面倒で決まったお皿しか出さない、そんな人もいるかもしれないが、それでは味気ない。食事では彩りや盛り付けといった見た目も重要な要素のひとつであり、器もその一端を担っている。だからこそ、食卓を彩るニッポンの器があれば、それだけで暮らしが自然と豊かになるのだ。世界に誇れる、深みのある器に触れていく。
Photos : TATSUYA YAMANAKA(stanford)
Styling : YONOSUKE KIKUCHI
Model : KENSEI MIKAMI
Text : SHINSUKE UMENAKA
撮影協力:野外博物館 合掌造り民家園、飛騨高山の陶磁器・渋草焼「芳国舎」

日本には全国に焼き物の産地がある。「六古窯(ろっこよう)」という言葉があるように、瀬戸、常滑、越前、信楽、丹波、備前の6つの地域には中世から生産を続ける窯があることで知られる。それ以外にも、栃木の益子焼、岐阜の美濃焼、石川の九谷焼、山口の萩焼など、名のある産地は多い。そんなメジャーな焼き物から器デビューするのも悪くないが、ふらりと訪れた旅先で地域に根ざした焼き物を探してみるのも楽しい。岐阜といえば、東濃地方で作られている美濃焼が有名だが、飛騨高山には渋草焼という焼き物がある。今回は、この渋草焼を紹介しよう。

渋草焼について詳しく語る前に、陶器と磁器の違いに触れておきたい。焼き物は、陶器と磁器の二つに大別され、原材料が最大の違いである。陶器は「土もの」と呼ばれ、陶土(粘土)から作られるが、対する磁器は陶石と呼ばれる石の一種を砕いて原料にしている。粘土から作る陶器は優しい雰囲気があり、素朴な作風が多いが、陶石から作る陶器はシャープな見た目で、表面もつるんとしている。そのため、繊細な色つけが施された作風が多いという特徴があるのだ。こうした基本的な知識を身につけておくだけでも、器選びがグンと楽しくなるだろう。


渋草焼は、1841年に当時の飛騨高山を治めていた、豊田藤之進が地元に新たな産業を興そうと、陶磁器の製産を御用商人に計画させて、現在の陶房がある「渋草」という地区に、半官半民の陶磁器製造所を開窯させたのがはじまりだと言われている。開窯にあたって、陶工を九州肥前の唐津から、絵師も加賀の九谷から、さらに尾張瀬戸からも戸田柳造など、各地から職人を集めることで品質を高めていったという。そんな渋草焼の特徴は、九谷や有田、京都、瀬戸、そして美濃の手法から学んだ深みのある白い膚の磁器と、独特な渋草調だ。加えて、昔ながらの手造りによる手描きにこだわっている。そのため素朴さをもちつつも、繊細な絵付けが見てとれる。

1841年に生まれた渋草焼だが、いまなお、その伝統を継承する職人によって、ひとつひとつ手作りで製造されている。ろくろで成形し、素焼き。その後、下絵をつけ、本焼きを行う。そして、上絵具を使って上絵付をしたら、もう一度、9時間ほど焼くと完成する。いずれも手作業で行うため、量産することはできない。そのこだわりを実直に、いまも守り続けている。そんな思いのこもった器は、食卓に彩りを与えてくれるはずだ。製造元のひとつ、芳国舎の直営店は高山市の町並保存地区である上二之町にある。もし、飛騨高山を訪れたときには足を運んでみることをおすすめする。


アイテムで揃えたいだろう。職人たちのこだわりに感化され、背筋が伸びる思いがする。
僕らの心に響く、こだわりや主張のあるニッポン×ファッションを着ようではないか。


























