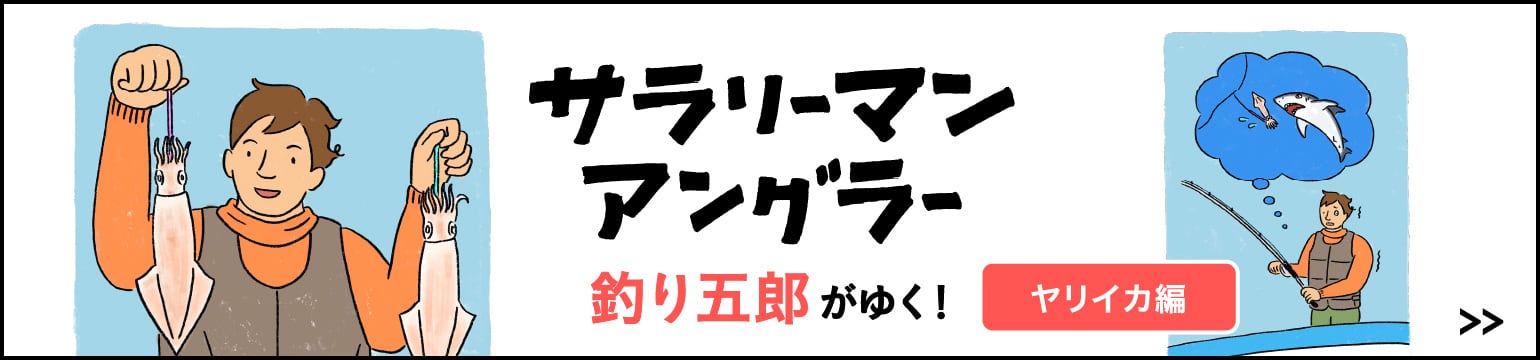時間の流れはあっという間。
時間をつくらないと
趣味も流れていってしまう
2020年、デビュー10周年を迎えた高橋優さん。10月にリリースされたアルバム『PERSONALITY』は、そのタイトルにふさわしく、パーソナルな内容が込められた歌詞と心にしみるメロディー、魂のこもる歌声の聴きごたえのある15曲が収録されている。
「近年はありがたくも忙しい日々を過ごしていて、ツアーの移動中やライブが終わったあとのホテルで慌ただしく曲づくりをしていたんです。でも2020年はワンフレーズが思い浮かんだら、それを煮詰める時間が膨大にあって、アルバムに収録する楽曲を50曲以上から選ばなくてはいけなくなった。家で黙ってゆっくり曲づくりをする時間がある、というインディーズの頃のようでしたね」
自宅で過ごす時間が長くなったことで、新たな趣味も生まれたそう。
「今まで映画を観る以外に、趣味がなかったんです。以前から写真を撮りたいという思いがあったので、この機会にやってみようかと。例えば曲づくりをしていても時間ってあっという間に流れていってしまうし、時間をつくらないと趣味も流れていってしまうなと。だから、今は“撮ろう”と思って、時間をつくって撮っています。今はジムに行って帰りの15分を“カメラタイム”にしています」

愛用のフィルムカメラは、「ニコンFE2」と「オリンパスペンEES-2」。
「フィルムカメラって24枚撮りのフィルムを入れたら、24枚しか撮れないわけだから、“何を撮ろうかな?”という気分も高まるし、撮ったあと現像に出して、どう撮れているのか見るのが本当に楽しみで。現像した写真を開ける時って、CDを買ってビニールを開けている時の感覚によく似ているんですよね。
今はまだ人を撮る勇気がなくて、壁とか撮ってます。僕はちょっとだけ廃墟が好きなんですが、ただ廃れている様子を撮るのではなく、“ここは華やかな場所だったんだな”と思わせる何かだったり、瓦礫の間から生えてる草だったり、何かキュンとくるようなものを撮るようにしています」
カメラは、これからもずっと“趣味にしていきたい”という高橋さん。もともと“モノにこだわる”人なのだろうか?
「僕は形から入るタイプの真逆で、今まではギターすら“弾ければいい”と思ってきたんです。1個1個のものを大事に使って、自分なりの使い方を見つけていきたいと思い始めたのは、ほんの最近ですよ。だって、まだ僕はこのカメラの機能を全部わかっていない(笑)。最近カメラマンの友達に聞いたりして、少しずつ撮り方を知っていっている感じ。
僕は中学生の頃は陸上部で、それ以来ずっとジョギングをやっているんですが、これも形にこだわり始めたのは一昨年くらいから。走る時なんて誰も見てないし、『走れればいいや』と思ってずっとボロボロの靴を履いて走っていたんです。でもせっかく頑張って走っているのに、こんなにみすぼらしい格好で走らなくてもいいかなって(笑)。昨年の駅伝で見て、ナイキの『ヴェイパーフライ』を3色そろえました。モチベーションもあがりましたね」


〝音楽を届ける〟という
純粋な気持ちに立ち返ったら、
形は問わない
現在放映中のドラマ『生きるとか死ぬとか父親とか』オープニングテーマ曲となる『ever since』は、配信シングルという形でリリース。現在の世界情勢となり、昨年からは配信ライブをする機会も増えた。
「ライブを行うほうの気持ちとしては正直いろいろありますが、『ライブに行こうか、スマホで観ようか?』と、観る側に選べる楽しさが増えたのはいいことだと思います。僕自身は、デジタルカメラの良さを知りながらフィルムカメラをやっているような人間ですし、根っこはアナログ(笑)。以前は音楽を聴く主な選択肢はCDだったけど、今は配信もある。『こういう曲をつくったので聞いてください』ということが僕の役目であるならば、聴いてくれるならばどんな手段でもうれしい。“音楽を届ける”という純粋な気持ちに立ち返ったら、形は問わないという気持ちです」
ドラマはジェーン・スー氏の著書を原作とするもの。『ever since』は原作を読んで、イメージを膨らませてできた曲なのだろうか。
「原作と台本を読んで、大まかなテーマは監督とお話しさせていただきました。でも原作は原作で、台本は台本。僕は僕の思いで曲にしました。多かれ少なかれ誰にでも家族のエピソードがあると思いますが、笑えるエピソード満載だけどただ笑わせるのではなくて、ほっこりさせたりヒリっとさせたり、原作は本当におもしろい。でもジェーン・スーさんの時代と僕の時代ではちょっと、時代背景が違うところがあるように感じましたね」
1983年生まれで、まさに“GOODA世代”※の高橋さん。自身では、この世代の人たちはどんな特徴があると思っているのか。※1973年~1986年頃生まれ
「僕らの世代は“はざまの世代”と言われていると思うんです。就職氷河期を経験して、根性を叩き込まれたであろう1970年代生まれの人たち。そしてそんな人たちに『ちょっと勘弁してよ』と言ってしまう“ゆとり世代”や、『要はこういうことじゃん?』って言えてしまう“さとり世代”が僕たちの後にくる。僕らはその間の世代で、どっちも経験しているからどっちの気持ちもわかる。そういう中継地点のような思いを表現したいから、何が正義か悪か、何が幸せで不幸せなのかといった、白黒をはっきりさせるような曲は僕は書きたくないんです。『どう思う?』って自分も含めて、みんなで考え続けていけるような曲を書いていきたいと思っています」

「優しい人だけど、優しさが下手な人」。『ever since』の歌詞は、自身の親への思いを感じさせる。民謡家として活動する、高橋さんの父親とのエピソードを尋ねると……。
「父はバスの運転手をやっていたんですが、それ以前に歌手を目指していたことを僕も知ってました。僕が高校生の時、父に『勉強もしないで音楽ばかりやっていてどうするつもりなんだ!』と言われて、当時は反抗期ですから『夢半ばで諦めたような奴に言われる筋合いはない!』みたいなことを言ってしまったんです。その時父は何も言い返さなかった。その後、僕が大学に入ってひとり暮らしを始めたら、父が“民謡で内閣総理大臣賞”とか民謡のタイトルを取り始めて。聞けば、3人きょうだいの一番下の僕が手を離れていったら、また夢の続きを始めようと思っていた、と。父親に『歌への思いは一度貯金していた』と言われて、泣きましたよ。それから、僕も父の民謡を聴きに行くようになりましたね。父は僕より先に武道館立ちましたから(笑)」
『ever since』の美しいメロディーと思いやりにあふれた歌詞。“優しい”中にも、チクリと胸を刺す、誰もが身に覚えがあるような感情を表現した歌詞があるのも印象的だ。
「優しいってややこしい言葉ですよね。優しくするつもりがなかったことに“優しい”と言われることもあるし、エレキギターが響くハードなナンバーを“優しい”と思う人もいる。僕は“優しい味”って、そこまで褒め言葉じゃない気がしていて。その人にとって必要なものを押しつけるのではなく、空気のように提供し続けさせることができたら、それはひとつの優しさなのかもしれないけど。『優しい人間であって欲しい』と“優”という名前をつけられている僕は、この言葉についてずっと考えているんです。“優しくありたいけど、優しさとは何なのか?” 僕はこの言葉を背負って、これからも生きていくんだと思います」