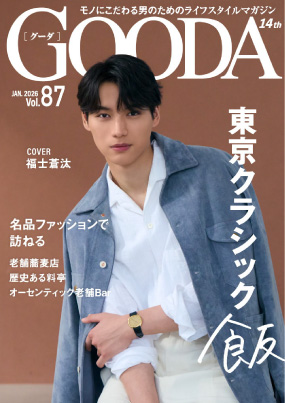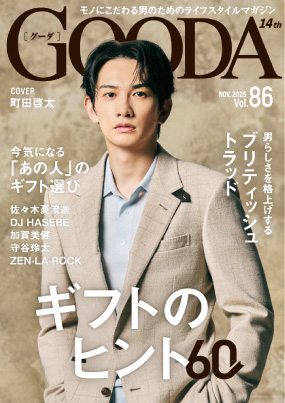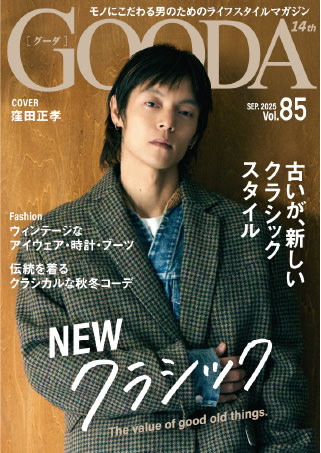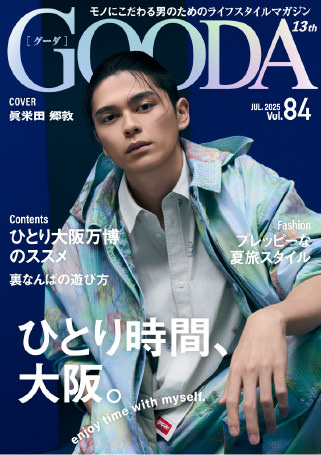ファッション
こだわりの藍染ウェアは畑からつくる。藍染の魅力を伝える「(terroir)テロワール」というブランド
2025.11.06
藍染の洋服というと、どんなイメージをもっているだろうか、独特の雰囲気をもつ深い青色、そして優しさを感じる淡い水色、その表情はさまざまで藍染でなければ表現できない雰囲気がある。
そんな藍染の洋服を畑からつくるという、ほかではあまり見られないような、こだわりのブランド「(terroir)テロワール」を紹介したい。
今回は「藍屋テロワール」代表の藤井健太さんに藍栽培のこと、藍染のこと、そしてブランドのことなど、お話を伺った。
取材/TAKANORI ITO

藍屋テロワール代表の藤井 健太さん
藍栽培から、藍染めまでを一貫してやる
——最初にブランドをはじめたきっかけから教えていただけますか?
「ブランドをはじめたのは2023年になるのですが、その前に、藍染の仕事を2019年からはじめました。日本で藍染というと徳島県が産地なので、徳島で2年ぐらい藍栽培の勉強させてもらいました」
——畑から一貫してブランドまでやっているのは、珍しい取組みだと思うのですが。
「藍の栽培と染は基本分業なので、栽培し、染料をつくり、染めまで一貫してやっているところは、あまり多くはないと思います。
藍を栽培し、染めの原料を卸すだけのお仕事だと大量に栽培しなければいけなく、最初から畑を何面も借りられたわけではないので、藍の栽培から染めまでやるというのは開業当時からのプランでした。いまは畑の面積も増やしてやっています。
日本では蓼藍(タデアイ)という品種が主に育てられています。強い植物ではあるので、わりと土地を選ばずに育ってくれるのですが、最近は暑すぎたり雨が降らなかったりということもあって、試行錯誤しながらやっている感じです。
栽培から染料ができるまでに1年という時間がかかるので、最初の1年は栽培と染料をつくることに専念しました」

藍の葉
藍染の原料ができるまで
——収穫した藍から染料ができるまでの工程を教えてください。
「夏の3か月の間に藍を収穫して、それを細かく刻んで送風機で風を起こして飛ばすんです。葉っぱは軽いので、遠くに飛んで、茎は手前に落ちるので、そうやって選別します。色は葉っぱにしか出ないので、こうして葉っぱだけを集めるんです。
そしてビニールハウスの中で平干しにして、乾いたらそれを保管して、また次に収穫したものを平干しにしてというふうに、収穫と乾燥を繰り返して、夏のあいだに乾燥葉をたくさん貯めておきます。
藍の葉は乾燥させるとその時点で青くなっていくんです」

藍の葉を収穫している様子

送風機を使い、葉と茎を選別している様子

藍の葉を平干ししている様子
「10月からはそれを発酵させます。山状に積んだ乾燥葉に水をかけ、葉っぱの菌によって水と酸素で自然に発酵させるのですが、1週間ぐらいで水分が抜けてくるので、山を崩して、水を打って、また山を積んでという作業を1週間に1回、1日がかりでやり、その作業を18回繰り返していきます。
発酵中は70℃ぐらいの熱をもつため、その山に筵(むしろ)をかけて熱が逃げないようにして発酵を促していきます。
発酵が終わると『蒅(すくも)』という藍染の原材料になります。これに灰汁、『ふすま』という小麦の皮、『貝灰』という貝を焼いた灰をミックスさせて藍染をしていくのですが、ここまでお話しさせていただいたこの藍染の原料づくりはとても歴史が深く、日本古来のもので奈良時代からあるといわれています」

蒅、ふすま、貝灰など
土地がもっている風土や、土地の特徴を大切にする(terroir)というブランド名
——さまざまなアパレルブランドなどから藍染の注文を受けながら、2023年にはオリジナルブランドとなる(terroir)がはじまるのですが、ブランドについてもお話しいただけますか?
「畑から製品まで一貫したものづくりをするということと、糸を藍染にして糸から生地をつくり、製品にしていくというのが(terroir)の特徴です。
藍染というと製品を染色液につけて染めるイメージがあるかと思うのですが、糸をさまざまな表情の藍の青に染めて、その糸で生地をつくっていくということをやっています」

糸を藍染している様子

さまざまな表情に藍染された糸
「つくっている洋服は、靴下、Tシャツ、スウェット フーディー、デニムパンツの4つ。僕らが屋号にしている(terroir)という名前は、それぞれの土地が持っている風土や、土地の特徴みたいなことを意味する言葉で、僕らが福山市という場所で畑からつくった藍であるということもそうだし、福山市がデニムの産地なので福山市でデニムもつくっていることもそうだし、編み物は和歌山県、靴下は奈良県など各産地の工場にお願いしてものづくりをしていくっていうのが一つのテーマでもありますね。
アパレルブランドをやりたいというよりは、藍染の良さを伝えていく手段としているので、デザインは極力シンプルにし、藍染にこだわり抜いたものをつくっています」

(terroir)ラインナップイメージ
藍染の魅力が詰まったこだわりのアイテムを紹介
——(terroir)のこだわりの4つのアイテムを紹介してください。
「一番の人気アイテムは『(socks)ソックス』です。藍染の糸を9色に染め分け、スラブ糸とよばれる不規則に節の入った白色の糸と共に編み立てることで、より藍が引き立ち、表情豊かな靴下に仕上がっています。
靴下生産量日本一を誇る奈良県広陵町で、旧式の編機を使い、ゆっくりと編み立てられたローゲージソックスは、ふっくらと柔らかく、肉厚な生地は伸縮性があり通気性も良く、季節を問わず履くことができるものになっています」

(socks) 5,500円
「そして『(hoodie)フーディー』と『(tee)ティー』は丸編みニット生産量日本一を誇る和歌山県で、吊り編み機によってゆっくりと編み立てられた生地を使用し、藍色と共に使い込むごとに体に馴染んでいくアイテムになています。
(hoodie)は藍染の糸を表側だけに使い、裏糸を白にすることで糸染ならではの特徴的なものになっています。生地は柔らかく、肉厚に仕上がっています。
そして(tee)は一枚でも着ることができる軽すぎない生地と、インナーとしても着ることができる細身のシルエットが特徴です。 ボディ、リブ、縫製糸の全てに藍染めされた糸を使い、経年変化を存分に楽しめる製品となっています」


(hoodie) 198,000円(税込)

(tee) 55,000円(税込)
「更に『(jeans)ジーンズ』に関してはパターンオーダーによる受注生産という販売方法をとっています。
ブランドを代表するようなアイテムなので、僕らの活動内容を知り、実際に現地に足を運んでくれて、畑だったり、染め場だったり、作業や仕事を見てくれて、(terroir)を応援してくれる方々がオーダーをくれたりしてます。
デニム生産量日本一を誇る広島県福山市でつくられるこの製品は通常のデニムとは違い、糸の芯まで一本一本、手染めしたことによって生まれる緩やかな経年変化と独特な表情の色落ちで、ゆっくりと織られた柔らかい生地が特徴になっています」


(jeans) 275,000円(税込)
藍染のワークショップを通して広く知ってもらいたい
——今後、ブランドとして、もしくは藍染でやりたいことなどありますか?
「今年10月に東京ではじめて藍染のワークショップを行ったのですが、いろいろな方に実際に藍染というものに触れてもらう機会として、こういう場所にくることも、1つの大きな活動だと思います。
以前は韓国とドイツでも藍染のワークショップをさせてもらったことがあります。
韓国は仲良くさせてもらっているデニムブランドの方が呼んでくれて、ドイツはベルリンで行われた展示会に呼んでもらいました。
藍染というのは日本特有のものでして、この藍染の良さを日本はもちろん海外にも広めて行きたいと思います」
藤井さんの藍染へのこだわりが、たくさん詰まったお話しを伺うことができた。
藍栽培から始まり、奈良時代から続くという昔ながらの方法で原材料をつくり、藍染の良さを伝える(terroir)いうブランドまでをつくったその藍染への愛が十分に感じられた。
藍屋テロワール、そして藍染ブランド(terroir)。この文化とブランドを日本、そして広く世界に知ってほしい。

藍屋テロワール
広島県福山市山野町山野3410
営業時間 10:00–17:00(日曜定休)
※随時、藍染体験の予約を承っています。
時期により、畑や蒅作りの様子も見学いただけます。
※(terroir)の商品はオフィシャルECサイトでお求めいただけます。