


江戸時代から日本人に愛され続ける「うなぎ」。夏の土用丑の日に限らず、ときどき無性に食べたくなる、“ヤミツキ”の味わいを持つソウルフードといえる。専門店でしか食べられない味を自宅でも手軽に楽しんでもらいたいと、兼光水産株式会社が手がけた蒲焼きが好評だ。コスパの良さが反響を呼び、ネット通販でリピート客が続出中だそう。その背景には、養殖から焼きまで徹底的にこだわり、美味しさと安心を追及し続けるひたむきな努力があった。
養鰻日本一の愛知県一色産うなぎを
一貫生産でお届け
今や日本人が食するうなぎの99%が養殖時代。稀少な天然うなぎは保護され、養鰻家(ようまんか)が育てた国産うなぎがその味わいとともに定着している。鹿児島、愛知、宮崎が日本三大鰻産地。なかでも全国の約25%を生産しているのが愛知県西尾市一色町で、市町村別1位を誇る。名古屋めしの「ひつまぶし」の発展にも一色産うなぎが貢献している。
その一色町から、オリジナルの蒲焼きを展開しているのが兼光水産だ。主力製品は、ガス火焼きの『うなぎ蒲焼き』と炭火で焼き上げる『炭火手焼き蒲焼き』の2種類。長年、養鰻と卸業を営む兼光淡水魚株式会社を親会社に、良質で安心、安全な製品を提供する体制で作り上げている。
「稚魚のシラスウナギの在庫管理から養殖、生産までをグループ全体で一貫して行っているのがウチの強みです。7~9月の繁忙期は、毎日3トンの活鰻を蒲焼きにしています」そう語るのは、製造課の野上大介さん。

3トンはうなぎ約1万2,000尾分。すごい数だが、割きの工程はすべて手作業で行っている。冷凍真空パック売りといっても鮮度が命。肝や骨を取り除いたうなぎは、一部を炭火手焼き用に金串打ちするほか、大半は量産用ラインへと素早く運ばれる。
そして製造ラインに規則正しく並べられ、まず上火下火のダブルバーナーで白焼きをする。700~800℃で強く焼きを入れ、余分な脂を落として香ばしく仕上げるのが兼光水産流だ。その後、湯気をふんだんに浴びせながら、ふっくらと蒸し上げていく。

蒲焼き工程は、機械ながらも職人技のよう。最初にさらりとしたたれにかける。そして焼き→たれの工程をさらに2回繰り返し、最後にとろりとした濃いたれを満遍なくかけて仕上げる。うなぎは美しい照りをまとい、熱々のままラインを昇り急速冷凍へ向かう。一連の流れに一切のムダはない。ライン作業にも関わらず、丁寧なのだ。
「毎日、加工前にはテスト焼きして、試食を行い合格したものだけを使っています。焼きや蒸しの時間は、うなぎの時期や大きさごとに変えますね。加熱時は1時間おきに中心温度のチェックも欠かしません」と野上さんは当たり前のように話す。
効率を追求しながら、品質も徹底管理。売れている理由は、味もさることながら誠実な企業姿勢に裏打ちされている。

炭火で手焼きすることで、職人の味を自宅で再現
工場で量産する傍ら、炭火で手焼きも行っているのが兼光水産の真骨頂。ライン設備とは別に設けられた炭火焼専用工場は、炭火ならではの香ばしい焼きの匂いに包まれている。グループの養鰻池で養殖された活鰻を使用するのはガス火焼きのライン設備と同様だが、割いた後は金串を打ち、自社設計の炭火窯で職人たちが手焼きするのだ。

主な燃料は備長炭。「外はぱりっ、中はふわっ」という焼き加減は、これをなくして成立しない。1000℃近い高温と遠赤外線効果でうなぎの芯まで火を通し、表、裏と何度も焼き返す。炭火窯の周辺は常に40℃以上と高温だ。夏場は水分補給をしっかりしながら、一日200kgを焼き上げる。
「『炭火手焼き蒲焼き』の200kgは、うなぎ800尾分です。一日100人来店するうなぎ屋さんでも、手焼きできるのは100尾前後。ですから職人たちの技術修得度は速いですね。たれは秘伝のたれの継ぎ足しです。焼き上がったらたれにつけて炙り焼きし、重ねづけして仕上げています」
炭火焼専門工場はうなぎ屋のような外観で、格子窓から焼いている様子がうかがえる。工場前に店舗を構えるレストラン部門の「うなぎの兼光」から、お客様がのぞきに来ることも。

「レストランがあるから美味しそうに感じると思いますが、その逆なんです。兼光水産のノウハウがあるからこそ、レストランでもベストな味を提供できています。結局、私たちは活鰻を育てるところから始まっていますから、一尾一尾に思い入れがある。それがお客様に美味しく提供したい思いにつながっているんでしょうね」
兼光水産では外国人技能実習生を受け入れているが、炭火手焼き担当の実習生が5年の実習期間を終えて帰国する。これを機に、兼光水産ではベトナムに「うなぎの兼光 ホーチミン支店」を出店する運びとなった。「帰国する彼らが中心となって、兼光水産の蒲焼きを提供します。現地駐在員の方々に日本の味を楽しんでいただければ」と野上さんは目を輝かせる。
兼光水産のこだわりの味は、ネット販売だけでなく実店舗でも世界に広がっていく。
愛知県三河一色産 うなぎの兼光の商品はコチラ
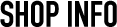

“皮目ぱりっ、中はふわ~”
職人がつくる極上の味を食卓へ








